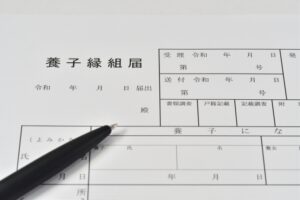相続登記と認知症の相続人について
令和6年9月15日の総務省の発表によると、高齢者人口は3,625万人、高齢者人口率は29.3%。日本の人口の約3割が高齢者となりました。
そして、平成29年度高齢者白書には2025年では高齢者の20%、5人に1人が認知症という予想が出ていますので、認知症の方も増加していると言えます。
当事務所の地域では一人暮らしのご高齢の方が年々増えており、空き家も増加傾向にあります。
空き家の中には、未亡人がお一人で住まわれていて、その後施設に入られて今は住まわれていないというケースも多いようです。
今は空き家になっている家の登記がどうなっているのかは分かりませんが、亡くなられたご主人の持ち家だった場合、相続登記をせずにご主人の名義のままになっている家は多いと思います。
最近までは、相続登記をしなくても法的な問題はありませんでしたが、令和6年の相続登記の義務化に伴い、自分が相続した事を知った時から3年以内に登記をしなければならなくなりました。
という訳で、今回は「認知症の相続人が居る場合の相続登記」について考えてみたいと思います。
相続の分配方法は次の3つのどれかとなります。
①法定相続分による相続
➁遺言書による相続
③遺産分割協議による相続
法務省が2018年に行った調査によると、日本人が遺言書を作成する割合は6.8%だそうです。約93%の人は遺言書を残していません。
つまり日本における相続は法定相続分か遺産分割協議のどちらかで手続きが行われるのが主流だと言えます。
まず、①の法定相続分ですがこれは法律に定められた遺産分割の割合の事です。配偶者と子供が法定相続人であれば配偶者1/2、子供は全員で1/2となります。これは相続発生時、つまり被相続人(亡くなった方)が亡くなった時が起点となります。法律で定められた権利です。
この割合を話し合いで変更するのが③の「遺産分割協議」です。法が定めた相続割合を変更するには、当然の事ながら意思能力のある相続人全員で話し合う必要があります。相続人に意思能力がない人、重度の認知症の人がいる場合は無効となります。認知症の方を含む遺産分割協議を行う場合には、家庭裁判所に後見開始の申立てを行って後見人を選任してもらい、後見人が認知症の方に代わって遺産分割協議に入る事になります。(「認知症と相続」についてはこちらをお読みください)
後見人が選任されると認知症の方の財産は一生後見人が管理する事になり、後見人には報酬を支払い続ける事になります。故に後見人制度の利用は余りされていないのが現状です。
という訳で、①の法定相続分による相続を選択する方が多いと思います。
法定相続通りの割合による相続登記の場合、相続人の中の一人が申請すれば相続登記は可能です。
公的な書類を収集、提出する必要はありますが、相続人全員での話し合い(協議)、署名などは不要です。
例えば、ご両親が持ち家(お父様名義)に住まわれていて、お父様が遺言書を残さず亡くなられ、相続登記をせずにお母様が継続して住まわれ、数年後お母様が重度の認知症を発症された。
そんな中、相続登記義務化に伴い相続登記の必要が生じた。
というような場合、お子さんのお一人が法定相続分通りの割合で相続登記を行う、というケースが今後増えてくると思います。
良く、不動産は共有にしない方が良い、と言いますが、現在の法律で認知症の相続人が居て後見人制度を回避しようとすると、法定相続分での相続登記を選ぶ事になり、共有不動産にならざるを得ません。
という訳で、相続人に意思能力を欠く方がいる状況で、法定相続分通りの相続や後見人制度を回避したい場合は、家の持ち主に、お元気なうちに遺言書の作成をしてもらうのが最良の方法となります。
既に家の持ち主がお亡くなりになっている(相続が発生している)場合は、認知症の方は遺産分割協議が出来ませんので法定相続分通りの相続登記を行い、その方が亡くなられた時に法定相続人全員で分割について話し合う事になると思います。
ただ、既に法定相続分通りの相続が確定した後の2回目の相続になりますので、もしお子さんが複数いらっしゃる場合でご両親と同居していたお子さんお一人が家の全てを相続したいと考えた場合、先の相続で既に共有不動産となっていますので、相続と贈与の両方を行う事になります。親の持ち分は相続、兄弟姉妹の持ち分は贈与となります。(「家族間贈与と贈与税」についてはこちら)
という訳で、お子さんが複数いらっしゃる方でその中の誰か一人に家を相続させたいと思われている方、配偶者が認知症または将来的に認知症になるかもしれないと不安な方は遺言書の作成をお薦めします。
そして、既に家の持ち主だった方がお亡くなりになっているご家族には、相続人全員がお元気なうちに遺産分割協議を行い、相続登記に着手される事をおすすめします。
なお、遺産分割協議がまとまらない場合、相続登記が完了しないという事になりますので、その対策として「相続人申告登記」という制度もあります。簡単に言えば、法務局に相続人の代表、責任者を登録しておくというものです。協議がまとまった時に相続登記をする義務がある事に変わりはありませんが、この制度を利用すれば、3年経過後の過料(10万円以下)は回避できる事をお知らせしておきます。
ほとんどの方は用意されていませんが、相続が発生した時にご遺族が困らないように遺言書を作成する事は大事な事です。
遺言書の作成、遺産分割協議など相続について、いつでもご相談ください。